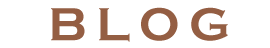点心料理教室
-
豆鼓醤の教室
2024.06.16
この投稿をInstagramで見る昨日は、特別教室で、自家製豆鼓醤のクラス。
にんにくを炒めながらシンプルに作った豆鼓醤は、驚くほど美味しく、おつまみにしたいくらいです。
そして、豆鼓醤で作る四川麻婆豆腐。材料にこだわって、火の通し方や豆腐の扱いにも細心の注意をはらい、〇〇飯店にも負けない麻婆豆腐が完成して、フライパンふってくれたA山さんに感謝、素晴らしい!!。そして、麻婆豆腐を作る時にできる肉味噌で作るエスニックサラダ。サッパリと合います。
デザートはさつまいもプリンで、豆鼓キャラメルソースがけ。このソースはここくらふとだけのオリジナルで、アイスにもかけたいと大好評でした。
この日はご飯もたくさんご用意したので、お腹を空かせて来るようお願いしました。「お店の味」と喜んでいただき、クラフトビール飲みながら汗をかきかき麻婆豆腐に舌鼓をうっていた生徒さんも。
点心の日と違ってこの日のお持ち帰りは、豆鼓醤だけでしたが、色々なtakeawayがあったのではないかと思います。
-
広東腸詰
2024.04.16
新しいレッスンのための実験。これから干します。
この投稿をInstagramで見る広東腸詰、中国腸詰って何?という人はこちら→https://www.tsuji.ac.jp/column/cat658/post-508.html
-
潮州餃子のこと
2024.03.15

16日土曜日の特別教室は潮州風餃子(潮州粉果)を作るのですが、いつもは満席になるはずの新メニューの教室に空席がたくさんあり、あまり人気がありません。
それもそのはず。潮州餃子は日本ではあまりないし、名前も地味だし何だっペって感じです。でも香港ではメジャーな点心で食べたことがある人にしかあのとろとろもちもち感はわからないと思います。
それだけならまだいいのですが、作るのが超絶難しいので、上級者でもかなり苦戦をしいられるかなと思います。ので参加条件(レベル)をつけるのも意味がないかもしれません。
水分を減らしたバージョンレシピも紹介しようか色々悩みますが明日最後の調整をして、土曜日に臨もうと思います。
今日の試作もかつてなく生地がトロトロになり、めっちゃ美味しかったけどめっちゃ難しかったです。
というわけで申込みを促進したいから書いたのではなく、よほど興味がない限り、申し込まないほうがいいかも、というお願いでもあるかもしれません。
潮州餃子をたべたことがあって大好きで、だから作りたいんです!という熱意のある人限定で開催できれば。それぐらい、地道に超絶技巧です。そして、地味に激ウマです。
香港に行ったらぜひ食べてほしいです。あ、うちの店でも時々だしますのでぜひお召し上がりください。
-
点心をビジネスとして身を立てること
2024.01.11
今年のお正月明けから、ここくらふと点心教室は新たな生徒さんたちを迎え、にぎやかな日々を送っています。多くの熱心な方々が参加されています。
趣味として点心づくりを楽しむ方は多いですが、当教室ではビジネスコースも提供しています。このコースは、飲食店の開業や料理の指導を目指す方々向けのプロフェッショナルコースです。参加者は限られていますが、常に一定数の方が学んでいます。
このコースが難しいかとよく聞かれますが、内容自体は一般コースと大きく変わりません。ただし、スキルの徹底的な習得を目指すため、落第して再受講するシステムがあります。できるまで次に進めないという意味では、厳しいです。ビジネスコース専用の講座も選択可能で、点心レッスンの動画視聴や個別フィードバック、最終的な卒業試験など、豊富なリソースが提供されます。
もちろん、飲食店で働いている方や、すでに料理講師の方もいます。また、「いつか開店したい」と考えている方や、ただスキルを磨きたいという方も参加されています。先日は、オーナーが酒好きだから合うだろうという理由でビジネスコースに入った方もいました。動機は人それぞれです。
当教室の目指すところは、生徒さんが点心の基本技術を習得し、オリジナルレシピを作れるようになることです。
ただし、技術を身につけただけでは、ビジネスの成功は保証されません。お店や教室を開いた後の集客は大きな課題です。客は新しいビジネスを知らないのです。だから来店もしません。料理人としてのブランド力がなければ、集客や販促が必要です。
店の立地も重要で、一等地は家賃が高く、それだけで集客が見込める場合もありますが、高い家賃を払うために集客や販促の努力がさらに必要です。より一層の施策が求められます。チラシ配布、ウェブサイトのSEO対策、SNS広告などが挙げられます。
店舗運営には、仕入れ、発注、在庫管理、プライシング、メニュー作成、スタッフ管理、レシピ開発、給与計算など、営業時間外の作業が山ほどあります。新メニューが出れば、写真撮影、ブログやSNSへの投稿、時には動画作成も必要です。内装や料理のスタイリングも重要で、お客様が心地よい空間作りが求められます。
営業も大切で、顧客になりそうな人々にショップカードを配ったり、地元の企業とのタイアップを考えたりすることも有効です。さまざまな販促プロモーションを実施し、お客様にリピートしていただくための努力も必要です。
というわけで、ビジネスを始めると、料理をする時間が減るという現実に直面することになります。ここが大きな会社組織との大きな違いでしょう。これはビジネスコースで詳しくお伝えしたいところですが、実際にはそのような細かな部分まで手が回らないことがあります。ですが、何でも質問していただければ、可能な限りお答えします。
点心に限らず、料理技術を身につけることは大切ですが、それ以上にビジネススキルが必要になります。料理の腕前だけではなく、ビジネスを運営するためのさまざまなスキルを身につけることが成功への鍵です。
(つづく かも)
https://coubic.com/cococraft/products/571596#pageContent

-
ここくらふと点心教室動画: 魅了される中華点心とプロの技の世界へ。今日も和気あいあいと学んでます。
2023.12.28
ここくらふと点心教室: 魅了される中華点心とプロの技の世界へ。今日も和気あいあいと学んでます。ここくらふと点心教室の動画
東京市ヶ谷にある、ここくらふと点心教室の紹介動画へようこそ!。点心レストランが教える点心教室です。実際に教室での様子を撮影したものです。2023年改訂バージョンです。
湯葉のオイスターソース蒸しや、とても難易度の高い蜂巣芋角(広東風コロッケ)を作るレッスンですが、生徒のみんなは和気あいあいと楽しく進めています。生地をこねたり、伸ばしたり、包んだり、揚げたり、いろんなことをするレッスンの回でした。
このクラスは中華点心が大好きで、点心の技術をもっと高く身につけたい、お店のように美味しく作って食べたい、という人たちに人気のクラスです。お店のレシピも多数紹介しますし、お店ならではの大きな麺台のテーブルなど設備も充実しています。そして、無添加、無化調で安心安全でおいしい点心作りを行います。
-
叉焼包(チャーシューマン)作りの秘訣 – 点心教室上級クラスレポート
2023.12.06

教室で作った生徒さんたちの叉焼包 今日は、点心教室上級クラスの第三回、叉焼包(チャーシューマン)のレッスンでした。点心の世界での最難関の一つとされる叉焼包は、誰もが一度は完璧に作りたいと思うアイテムです。
1.自家培養発酵生地の重要性

生徒の皆さんが持参した自家培養の老麺(発酵生地)で作った叉焼包は、まずまずの出来栄えでした。完璧に上まで膨らみ、ふかふかに割れる生地を作るためには、老麺の状態が非常に重要です。培養の丁寧さが、最終的な品質に大きく影響します。ずっと冷蔵庫に入れっぱなしにして、受講の直前にだけ発酵させるのでは不十分です。マメに発酵させることが重要です。
よく発酵した老麺は、巣立ちが大きく、そして、生クリームのようにふわっとしているのです(写真)。
レッスンではこの老麺に砂糖などの材料を加え、とろーりとするまで活性化させます。この生地作りが時間がかかりとても大変なのです。
トロッとしたら小麦粉を加え、あとは、すぐに、餡を詰めて包みます。少し置いたら、せいろで高パワーで蒸します。
2.蒸篭のフタを開ける瞬間のドキドキ

どんなに準備をしても、蒸篭のフタを開ける瞬間はいつもドキドキします。時には、うまく割れなかった生徒さんががっかりされて、「次はもっと頑張ります!」と健気におっしゃいます。まあ、一朝一夕に完璧に作れるものではないのです。まずは叉焼包を作ったことをまずは満足いただいて、焦らずにまた取り組んでいただければいいかなと思います。
3.特別な味わい:手作り叉焼包
手作りの叉焼包は本当に特別です。ベルギーエシャロットで香りを出した叉焼用の醤は、旨味たっぷりで、自家製の叉焼とも絶妙にマッチします。叉焼醤は冷凍しておくといいですね。色々な用途にも使えます。
ちなみに、お店でも叉焼包は定番メニューとして提供しています。この秋からは、中の叉焼を広東風に焼き上げて、さらにバージョンアップしています。
-
餃子のヒダの作り方
2023.12.05

焼き餃子の包み方 今日の点心教室初級では、皮から打つ手打ち焼き餃子作りに挑戦しました。
焼き餃子の包み方にはコツがあります。通常は外側の生地をたわませて内側にくつけますが、中には手前側で包む方もいます。
ストレスを感じさせないよう、やりやすい方法を推奨していますが、エビ蒸し餃子のような他の点心では外側でヒダを作る方が適していると説明しています。
今日の生徒さん人は、通常とは異なる手前側で作る方だったのですが、せっかくだからと普段はしない外側でのヒダづくりにチャレンジされてました。どちら側も上手にヒダが作れ、見事な焼き餃子を作り上げました。
手前側でヒダを作ると親指の動きが中心となります。外側でヒダを作る方法では人差し指の中心となり、全く違う指を使うのです。
点心作りでは、特に小籠包のような細かい作業では、人差し指を使う技術が重要です。左手でヒダを送りながら右手で形作る方法よりも、利き手の人差し指だけを使う方が上達が早いです。
焼き餃子の場合も、理想的には左手でヒダを送らず、左の人差し指を皮の外側に置き、右手の人差し指だけでつまむと、より美しい三日月型が作れます。
もちろん、焼き餃子は独自の形があり、必ずしも三日月型にする必要はありません。
質問があれば、お気軽にお問い合わせください。
Youtube チャンネル 手打ち焼き餃子 皮の伸ばし方包み方
-
2023年点心おせち教室~現代的おもてなしの饗宴
2023.11.27

点心おせち教室2023 ここくらふと点心教室では、毎年恒例の点心おせち教室を12月に開催します。さらに、今年はパワーアップした内容で、メニューを一新、数も増やしました。
伝統的な点心を斬新なおせち料理へと変化させます。つまり、ここでしか体験できない、オリジナルなアレンジの数々です。そして、点心の基本技術から、おせち特有の飾り切りや盛りつけの技術まで、総合的なレッスンを提供します。
※参加者はご自身のお重をお持ちください(目安は2段)。作成したおせちをお持ち帰りいただけます。
開催日:12月19日(火)と23日(土)、12:00〜17:00
料金:12,000円
受講資格:当教室中級以上の経験者(中級受講者または終了者)
予約ページ(外部サイト):https://coubic.com/cococraft/4394694#pageContent
メニュー:
写真左:寿桃包(桃饅頭)、腐皮蟹腸粉(蟹の揚げ湯葉の腸粉ロール)、鳳尾鮮蝦丸(ブラックタイガーのえび団子蒸し)、四喜焼売、錦糸焼売。下段には陳皮牛肉球とお煮しめ、中国湯葉入り紅白なます、
写真右:鴨ロース、揚げ魚の南蛮、そして祝い肴3種(黒豆と数の子のマスカルポーネチーズ和え、たたきごぼう)があります。席はのこりわずか。この特別な機会をお見逃しなく!伝統と革新が融合したここくらふと点心教室での一日をぜひお楽しみください。