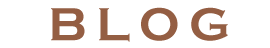ビール
-
志賀高原インディアンサマーセゾン,
2018.04.26

こんばんは、スタッフの渡邉です。
四月も終わりに近づき、GW目前となりました。皆様は今年のGWはどうお過ごしになるのでしょうか?
さて、今回は2つのビールを紹介いたします。
①志賀高原ビール Indian Summer Saison
夏を通り越して、晩秋の「インディアン・サマー」の季節までもつように、さらに、たっぷりのホップをつかって仕込んだこのビール。名前からセゾンビールを想像するかと思われますが、こちらのビールしっかりとしたパンチと苦味があります。しかし、度数を感じさせないドライな口当たりによりとても飲みやすいです。香りもグラスから漂う柑橘がとても心地よい一品です。
②常陸野ネストだいだいエール
久々復活した常陸野ネストビールだいだいエールは、常陸野の古の「福来みかん」を材料に、その香りを引き立たせる柑橘風味のホップで仕上げたビールです。こちらのビールは程よい苦味と飲み応えの中にみかんの美味しさを取り入れたCoCo Craftでも大変人気の高い一品です。
ぜひ市ヶ谷にお越しの際はCoCo Craftにお越しください。
-
新しいビールのご紹介♪アウトサイダーとブルームーン
2018.04.21
新しいビールのお知らせです。
1.アウトサイダー スプリングブレイク・ゴールデンエール
期間限定品です。モザイクホップを使ったグレープフルーツの様なアロマと白ワインの様ななめらかな口あたりが特長です。IBUは30と苦味は普通で、モルトの甘みがあり、バランスのいい飲みやすいビールだと思います。
そしてアウトサイダーらしい香りの良さが際立っています。スプリングブレイク、いかにも季節限定品ぽいですが、名前が横文字で長いので、店のメニューは、ゴールデンエール、と省略してます(汗)。
2.ブルームーン ベルジアンホワイト
ブルームーンといえば、ベルジアンホワイト。シトラスの香りあふれるフルーティな風味と、軽くスパイシーな小麦のアロマ。オレンジピール、コリアンダーはもちろん入っておりますが、加えて、オーツ麦が入っているのが特長で、これが複雑でクリーミーなミディアムボディを生み出しているようです。
新しいビールが入ったときに、アルバイトにブログを書いてもらおうと思いつつ、彼らが出勤してるときになかなか時間が取れません。彼らのフレッシュな書き込みをしてもらうためにもまたそのうち登場してもらいます。
今日一人面接があり、ここくらふとで勤務希望の学生がきました!また新しい顔をお披露目していければいいなと思います。お楽しみに。


-
田沢湖ぶなの森、さわやかに森林浴気分で心地よいビール
2018.04.12

田沢湖ビール「ぶなの森」開栓してます。
秋田県のぶなの木の樹液から分離させた天然酵母を使い、森林浴を感じさせるようなやさしい香りと味わいのエールです。発酵時間も通常の2-3倍とのことで、じっくり作ったビールということがよくわかります。
ドライな感じで飲みやすく最初の一杯にもおすすめです。こういうやさしくてライトタッチな味わいの独特なエールは田沢湖さんの得意なところかなと思います。
また、ぶなの森という名前も商品をイメージしやすくていいですね。昨日もお客さまとお話をしましたが、ビールの名前はわかりやすさがやはり大切ですね。横文字で長い名前は一見カッコよさそうでも、お客様の注文には即つながらず、なかなか樽が空かないこともあります。
ビールマニアなら名称は全く関係ないかもしれませんが、一般的には商品を選ぶときにわかりやすくて読みやすい名称の方をついつい頼んでしまうというのはよくあることで、それはひしひしと感じます。シンプルでわかりやすいのが一番で、ブルワリーさんもそうしたほうがいいのになと思います。
そんな自分も、前職では、まったく日本人には馴染まない、わけのわからない横文字のネーミングばかりつけていたので、今更ながら、笑ってしまいます。
-
新しいビール2種のご紹介!
2018.04.05

こんばんわ。スタッフの渡邉です。
桜が早々に散り、私は少し物足りないと感じている今日この頃ですが皆様はいかがお過ごしでしょうか?
CoCoCraftはそんな私の気持ちを吹き飛ばしてくれる新しい生樽を2つ用意しました。今回はその2つを紹介したいと思います。
①OUTSIDER マスカットベリーAサイダー(期間限定)
山形県甲州市勝沼町産のマスカットベリーAをふんだんに使用したビールです。グラスに注いだ瞬間から香るマスカットの香りと口に含んだ瞬間広がる程よい酸味。色は淡いパープルで、しっかりとマスカットの味わいを楽しみながら、アルコール度数4.5%と軽いあじわい、スッキリ飲めるビールとなっております。
②ヤッホーブルーイング よなよなエール
クラフトビールの王道の味わいを追求したアメリカンペールエール。フルーティな香りの秘密はカスケードホップ。万人に受ける上品でスッキリとした味わいは、CoCoCraftのどんな食べ物と合うビールです。ぜひ樽生の良さ、ワンランク上の安定した品質の素晴らしさを実感してください。
ぜひ市ヶ谷にお寄りの際はCoCoCraftにお越しください
-
近日公開 期間限定ビール
2018.03.21
こんばんわ。スタッフの片野です。主に週末などの非常勤(?)でカウンターに立っております。
厳しい冬がやっと緩んだと思ったら、出戻った冬将軍が威張り散らしている今週。
皆様はいかがお過ごしでしょうか。
とはいえ市ヶ谷は桜の蕾も膨らみ、春の訪れを町全体が喜んでいるようです。
そんな春の訪れを皆様にお楽しみ頂きたく、醸造元さんの季節限定ビールが
続々入荷予定です。その中で近日開栓予定の2品をご紹介します。
①六甲ビール
ここくらふと初お目見えの「六甲ビール」さん。
その中から限定醸造、その名も「春らんまん! さくらエール」が入ります。
柔らかなピンク色にさくらのフレーバー。微かに薫る柑橘系の香りが春を
感じさせてくれます。IBU28。
②箕面
逆にここくらふと定番の「箕面ビール」さんからは「Blooming IPA」が参上。
スパイシーでフローラルな醸造香と薫り高いアロマホップの組み合わせは、
春らしい薫り高い一杯となることでしょう。
スタイルはベルジャンIPAです。
どうぞお楽しみに!
-
アウトサイダー ミダスゴールデンエール開栓
2018.03.15
スタッフの渡邉です
日の出ている間はとても過ごしやすい季節になり、皆様はどうお過ごしでしょうか?私は今年から発症した花粉症に悩まされる日々です(泣)
さて本日よりOUTSIDERさんの幻のビール<MIDAS Golden ALe-ミダスゴールデンエール>が開栓します。山形県産桃から採取したワイルドイースト使用することによりグラスから香るほどのフルーティな香り。そして一口でわかる濃厚な味わいと口に広がるアルコール。
アルコール度数12%は伊達じゃありません。私は弱いので顔を真っ赤にしながら試飲しております(笑)、が、このビールのことや、他のビールのことで何か質問がありましたら遠慮なく聞いてください。
ミダスゴールデンエールは、デザートビールとしてもぴったりの一品です。ぜひCoCo Craftにお立ち寄りの際はお試しください。

-
田沢湖 東北魂的IPA開栓
2018.03.09

スタッフの稲宮です。
先日某商社さんの、日本初上陸のビールの試飲会に行ってまいりました。
近頃就職活動をしている身としては、こんな仕事もあるんだなと、
自分のこれからを考える良い機会になりました。
新ビールの導入については楽しみにお待ちください!。
さて現在東北のブルワリーでは、【東北魂】のプロモーションが実施されています。
同じレシピの同商品を、東北の各ブルワリーから発売するというものです。
きりっと苦いIPA感と、ほどよいモルトの口当たりが素晴らしいビールになっております。
CoCo Craftの点心と、田沢湖の東北魂IPAを合わせて、お召し上がりください。
-
入荷ビール
2018.03.03
ガージェリーのボトル、「ウィート」「エックスエール」入荷しました。本日より瓶は再び「ブラック」とともに3本揃います!瓶内熟成の生をお楽しみください。
定番の箕面のWIPAも、ちょっと切らしてしまいましたが、昨日無事開栓しました。フルーティな極上の香りと苦味とモルトの深い甘み、やはり人気が高いビールですね。
近日中入荷予定は富士桜高原ピルス、東北魂的IPAです。

-
金しゃち フルーツドラフトレモン開栓
2018.03.01
金しゃちビールの期間限定「フルーツドラフトレモン」開栓してます。評判がよかったので再生産となったもようです。レモンを丸ごと加えたような爽やかさ、酸っぱさ、皮の苦味を感じ、大変ナチュラルなテイストです。IBUは10と低いので、ホップそのものの苦味はあまりなく、飲みやすい仕上がりです。
昨日は飲み放題で結構な量が出ましたので、あまりもう量が残っていないかもーです!。
箕面のゆずじゃばらペールエールは限定で提供しているので、まだ残っています!

-
箕面 ゆずじゃばらペールエール開栓!
2018.02.23
スタッフの稲宮です!
本日箕面ビールさんの「ゆずじゃばらペールエール」を開栓いたしました。
じゃばらの苦味と酸味に柚子が加わって非常に香り高く仕上がっており、
かつ箕面ビール特有のまったりとした酵母感、そしてペールエールのほのかな甘みとキレが
非常に良くマッチしております。もちろん当店の点心との相性もバツグンです!
ぜひ市ヶ谷Coco Craftにお立ち寄りください。